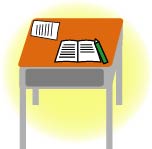新規生の様子を紹介します。
先週は、後期講座が開始し、久しぶりに通常クラスでの授業でした。
相変わらずみんなとても元気そうでした。年末年始でおばあちゃんのお家へ行ったこと、お年玉の使い道など色々話してくれました。また、たくさんおいしいものを食べたのでしょう。なんだか…お正月あけてすごく体格がよくなっている子も…。みんなとても楽しいお正月だったようです。
冬期講座が終了後、たくさん「楽しかった!」という声を聴くことができました。さらに嬉しいことに、冬期講座を受けた後、そのまま1月から通塾してくれている子もいます。先週、2年生の教室へ新規生(冬期講座に参加してくれた子)の様子を見に行ってきましたので、その時の授業の様子をご紹介します。
今回は、長さや重さの単位換算について学習しました。重さの単位換算は「1t=1000kg」「1kg=1000g」と分かりやすいのですが、長さの単位換算は、「1㎞=1000m」「1m=100cm」と桁数が異なるため難しいようです。 このような単元では、単に暗記するだけでなく、身近な場所の距離や身近な物の重さなど、繰り返し具体例をイメージしながら考えていくと理解が深まります。玉井式では、授業の映像がお子さんのイメージングをサポートすると共に、具体例を示しながら学習を進めています。しかし、イメージングの力は徐々に養われていくので、習いたての場合はまだ慣れないため混乱してしまう子も多く見られます。
このような単元では、単に暗記するだけでなく、身近な場所の距離や身近な物の重さなど、繰り返し具体例をイメージしながら考えていくと理解が深まります。玉井式では、授業の映像がお子さんのイメージングをサポートすると共に、具体例を示しながら学習を進めています。しかし、イメージングの力は徐々に養われていくので、習いたての場合はまだ慣れないため混乱してしまう子も多く見られます。
今回見学した授業でも、具体例をイメージしつつも、まだなかなか正しく単位換算できない子が多くみられました。そこで、先生が「1㎞=1000m」「1m=100cm」と色分けをして板書し、それを見ながら問題に取り組み、繰り返し確認していきました。ちょっとした板書でも「視覚的に分かり易い」ということは、低学年の授業ではとても大切なことだと改めて感じました。その板書を見ながら「赤は…青は…」と区別しながら取り組んでいる子もいました。
基本をしっかりとおさえることができたことが自信に繋がったようで、その後「ものがたり算数」など積極的に参加できました。今回は、みんなで主人公達になりきろうと、一人ずつ役を決めて音読しました。みんな自分のセリフがまわってくると張り切って読み、お母さん役になった男の子がお母さんになりきってセリフを言う場面では、抜群の演技力を発揮してくれ、みんな大笑いでした。新規生の子もクラスにもすっかり馴染め、笑顔で帰っていく姿を見てほっとしました(一番ほっとされたのはお迎えに来られたお母さんのようでした)。新しいお友達が増えて、みんなも嬉しそうでした。今後も体験を受けられるお子さんや新規生のお子さんも授業に楽しく参加できるようしっかりと見守っていきたいと感じた日でした。
(makino)