新漢字誕生?
今回は、3年生の授業の様子をご報告させていただきます。
今回の国語は、「漢字計算クイズ」という単元でした。これは、漢字をいくつかのパーツ(パーツの一つひとつが意味のある漢字、数字、カタカナでなくてはいけません)に分けて考え、それぞれたし算、ひき算、かけ算をすることで、一つの漢字を組み立てていくというものです。この活動により、漢字に親しみをもち、『漢字はいくつかの部分に分けられ、共通の部分があることを理解する』ことをねらいとしています。
今回の単元は単純な書き取り問題ではなく、漢字を計算問題として扱うという、これまでとは視点を変えた学習が取り入れられており、普段は漢字の学習を苦手としているお子さんも、興味をもって取り組むことができたようです。みんなとても楽しそうに「漢字の計算問題」を解いていき、また、自分で問題を作成することにも取り組みました。それにしても、子どもの思考力の柔軟性には驚かされますね。どれだけ独創的な問題を作成することができるか、各自が必死になって考えていました。中には、まず最初に答えをいくつも決めて、それに合う式を一生懸命考えているお子さんもいました。子ども達が集中して一つ一つ漢字の形を考えている姿を見ていると、改めて漢字って不思議な形だなと思えてきます。
 授業の最後には、スペシャル問題として少し難易度の高い問題を出しました。特に、「立+日+思-田=?」、「ノ×4+立+頭-豆=?」という問題には、ほとんどのお子さんが考え込んでいたため、途中で「これはヒントが必要かな?」という考えも頭をよぎりましたが、しばらく悩んだ後、子ども達は見事に正解を導き出しました。
授業の最後には、スペシャル問題として少し難易度の高い問題を出しました。特に、「立+日+思-田=?」、「ノ×4+立+頭-豆=?」という問題には、ほとんどのお子さんが考え込んでいたため、途中で「これはヒントが必要かな?」という考えも頭をよぎりましたが、しばらく悩んだ後、子ども達は見事に正解を導き出しました。
実は、 「これだけみんなでこだわって考えれば、もしかしたら新種の漢字が生まれるのでは?」と、授業の本来のねらいとは関係ないところで、密かに期待してしまいました![]() 私自身も子どもの頃、新しい漢字を作ろうとして友達と一緒に考えたような記憶がありますが、実際に現在使われている漢字が生み出された遠い昔も、もしかしたら同じような流れで考えだされたのかもしれませんね
私自身も子どもの頃、新しい漢字を作ろうとして友達と一緒に考えたような記憶がありますが、実際に現在使われている漢字が生み出された遠い昔も、もしかしたら同じような流れで考えだされたのかもしれませんね![]()
(butsuen)
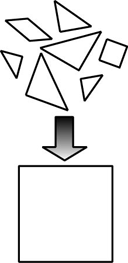 しかし、しばらくそのような状況が続いた後、一つのパズル教具を手にしたとき、Kくんの中で突如意欲がわいてきたらしく、目の色を変えて取り組み始めたのです。それ以降は、すぐ近くで他のお子さんが別の教具を使って楽しそうにしていても、Kくんはわき目も振らず、一生懸命に目の前のパズルに向かっていました。そして、何度も何度もパズルを組み直しながら15分間ほど経過した後、Kくんは見事に課題を完成させることができました。課題をクリアできていることを確認して、「すごいね、よくできたね。」と声をかけると、「やったー!これ難しいけぇ、もうできんかと思ったー
しかし、しばらくそのような状況が続いた後、一つのパズル教具を手にしたとき、Kくんの中で突如意欲がわいてきたらしく、目の色を変えて取り組み始めたのです。それ以降は、すぐ近くで他のお子さんが別の教具を使って楽しそうにしていても、Kくんはわき目も振らず、一生懸命に目の前のパズルに向かっていました。そして、何度も何度もパズルを組み直しながら15分間ほど経過した後、Kくんは見事に課題を完成させることができました。課題をクリアできていることを確認して、「すごいね、よくできたね。」と声をかけると、「やったー!これ難しいけぇ、もうできんかと思ったー ところで、そのクラスの中には、非常に元気の良いお子さんが2人いたのですが、お互いに強い対抗心を燃やしているらしく、課題プリントを解く時や答えを発表する際など、「もうできた!」「はい!1番!」などの声が聞こえてきます
ところで、そのクラスの中には、非常に元気の良いお子さんが2人いたのですが、お互いに強い対抗心を燃やしているらしく、課題プリントを解く時や答えを発表する際など、「もうできた!」「はい!1番!」などの声が聞こえてきます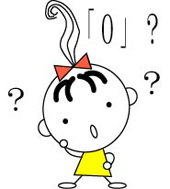 余談ですが、「0(れい)」の漢字として使われる「零」には、「極めて少ない」という意味も含まれるため、同じ「0」でも『ZERO』と『零』では、若干意味も異なるものになるのだとか。そのため、ニュースの天気予報等で、降水確率「0%」を通常「れいパーセント」と読んでいるのは、降水確率「ゼロ」%ではなく、「まったく雨が降らないわけではありません」という意味を含めている・・・という話を聞いたことがあります。「0」って、不思議な数字ですね(?_?)
余談ですが、「0(れい)」の漢字として使われる「零」には、「極めて少ない」という意味も含まれるため、同じ「0」でも『ZERO』と『零』では、若干意味も異なるものになるのだとか。そのため、ニュースの天気予報等で、降水確率「0%」を通常「れいパーセント」と読んでいるのは、降水確率「ゼロ」%ではなく、「まったく雨が降らないわけではありません」という意味を含めている・・・という話を聞いたことがあります。「0」って、不思議な数字ですね(?_?) 『メジン』→『目人(メジン)』→『頭が目になっている人』・・・【見】
『メジン』→『目人(メジン)』→『頭が目になっている人』・・・【見】


