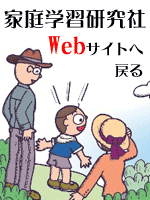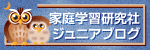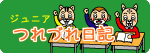2025 年 4 月 23 日
弊社の指導の枠組みのなかで最も新しく、斬新な手法を採用した学習指導の部門があるのをご存知でしょうか。カリキュラムやテキスト、テストの制度等は通学コースや土曜コースと共通ですが、Zoomを介して弊社の通学コースでも活躍している講師の授業を受け、家庭勉強と連動させながら中学入試での志望校合格を果たすことができます。この指導部門は、「オンラインコース」という呼称で4年ほど前から活動を始めていますが、すでに成果をあげており、広島の代表的な中高一貫校の全てに合格者を輩出しています(以下に、合格状況の一部をご紹介しています)

オンラインコース 2025年度中学入試合格状況 ※35名(男17名 女18名)
広島学院中8名、修道中10名、ノートルダム清心中6名、広島女学院中9名、
広島大学附属中7名、県立広島中3名、市立中等教育1名
言うまでもなく、中学受験は小学生の受験です。このことでさしあたって問題となるのは子どもが一人で通学できる環境にあるかどうかでしょう。通学距離や交通手段が障壁となり、通いたい塾への通学を断念されるご家庭もおありでしょう。また、スポーツや習い事との兼ね合いもあり、通学に時間をとられたくないというお子さんもおられるでしょう。さらには、「在宅学習で受験勉強ができるなら、そうしたい」という希望をおもちのご家庭もおありでしょう。弊社のオンラインコースは、きっとこれらに該当するご家庭のお役に立つと思います。
-
オンラインコースの特長
1.リアルタイム双方向型のライブ感ある授業
通学コース生と共通のテキストとカリキュラムに沿い、家庭でZoomを使ったオンラインのライブ授業を受けることができます。授業中に指導講師からの発問と受講生の応答もあり、教室指導と遜色のない緊張感のある授業を実現しています。
2.授業前のホームルームでコミュニケーションの態勢も万全!
毎回の授業前にホームルームを実施し、受講生に授業で扱う単元の内容理解に向けた前知識を提供したりアドバイスをしたりします。これによって指導講師とのコミュニケーション態勢も整い、食いつきのよい効果的授業を実現します。
3.欠席時のフォロー、質問への対応も心配無用!
その日の都合や体調等で授業をお休みになったときや、理解が不十分な回があったときにはサポート動画でフォローします。また、専用電話の設置やメールによる交信で、いつでも質問や相談ができる態勢を整えています。
4.マナビーテストとの連結で学力状態も掌握できる!
受験勉強に必須なのがテストの制度とデータですが、オンラインコース生も通学コース生と共通のテストを受け、同じ条件で処理されたデータを得ることができます。また、希望者は校舎でテストを受けることも可能です。
5.保護者面談もオンラインで実施
小学生の受験勉強には保護者のサポートが欠かせません。その際、対処に困惑される問題も生じることでしょう。このような保護者にはオンライン面談を実施しています。担当者は中学受験を熟知したベテランですから、状況に応じた適切なアドバイスをすることが可能です。
このほか、もっと問題に取り組みたいお子さんにはプリントのダウンロードで応じるサービスも行っています。また、なかには公立中高一貫校への受検も併せて検討されるご家庭もおありでしょう。そのようなご家庭への対応も可能です。上記実績にもあるように、合格者も出ています。塾への通学をせずに中学入試を突破したいお子さんにとって心強い味方となるのが、このオンラインコースです。
ただし、周囲に同じ目標をもつ仲間がいて、ともに学び励まし合うことのできる通学コースには、相応のよさや魅力があります。また、指導する講師と直接触れ合うことで得られる刺激や細かいアドバイスは、通学コースならではのものです。両方のよさや特色をよくご理解のうえ、お子さんの生活条件や考えに適したコースを選定していただくようお願いいたします。
弊社のオンラインコースの詳しい内容や入会方法等については、こちらをクリックしてください。
オンラインコースについて
また、5月24日(土)に“中学受験ガイダンス”をオンラインで行います。
中学受験についてまだ知らないけれども興味がある。
広島の中学受験について知りたい。
こどもにとっての成長できる中学受験について知りたい。
一つでも当てはまる方はぜひご参加ください。
オンラインコースについてもご説明いたします。
オンラインコース、授業体験(算数)も希望者は受講可能です。
広島中学受験ガイダンス(オンライン開催)5/24(土)について
カテゴリー: お知らせ, 中学受験, 家庭学習研究社の特徴, 行事のお知らせ
2025 年 4 月 4 日
2025年前期の講座が開講して1カ月余りが経過しました。お子さんは家庭勉強と塾の授業(週3日コース)、マナビーテストのサイクルを受け入れ、受験生活を軌道に乗せるべくがんばっておられるでしょうか。すでに2回ほど学習成果を競い合うマナビーテストが実施されましたが、その結果に手応えを感じているお子さんもいれば、逆にがっかりしているお子さんもおられるでしょう。
弊社は50年以上前の創設時から、「子どもの自立学習支援」という方針を掲げて中学受験指導を行っています。それは、中学進学後の学習環境や、将来の人生の歩みを視野に入れ、「絶対に必要だ」と考えたからです。学習が質量ともにハイレベルな中高一貫校では、自己管理のもとで勉強をやりこなせるかどうかが成果に覿面に現れます。また、進度の速い学習ペースになじむ過程では、幾度も壁にぶつかったり、悩みが生じたりするものです。このような環境に適応するためにも、できるだけ子ども自身が勉強を自分のこととして受け止め、自ら勉強をやりこなそうという姿勢を築いておいたほうが望ましいのではないでしょうか。しかしながら、みなさんご存知のように小学生にとって自立勉強は難しいものです。
実際のところ、弊社の教室に通う子どもたちはどの程度学習の自立を果たしているのでしょうか。 正直申し上げて、受験生活のはじめから終わりまで、すべて自分で勉強をやり通せる子どもは皆無でしょう。勉強の手順をいくら子どもに伝えても、結構な難度と分量のある学習を毎日のルーチンとして定着させるのは簡単ではありません。また、カリキュラムに沿って学習計画を立てても、達成度は子どもそれぞれに異なります。状況に合わせた修正も必要です。なかには早々に行き詰まりを感じているご家庭がおありかもしれませんね。しかし、ここががんばりどころです。お子さんは、やるべきことがわかっていますか? 決めた時間枠のなかで最善の努力をしておられますか? 焦る必要はありません。お子さんが今できる精一杯の勉強をするよう励ましてあげてください。
親の立場に立つと、要領を得ない子どものまどろっこしい試行錯誤のプロセスを見守るのは精神的に辛いものです。しかし、学びの自立に向けた日々のもどかしい取り組みのプロセスにこそ意味があるのだとお考えください。成長途上期に自らを鍛える経験を積み重ねると、子どもは見違えるほど変わっていきます。大人の目から見ると不十分な勉強でも決して無駄にはなりません。心身共に大きく変わっていく時期に、心血注いで勉強に取り組んだなら、それが子どもの頭脳の成長に反映されないはずがありません。
今の段階で保護者にとっての重要な視点は、「わが子は何をすべきかわかっているか」「学習計画に沿って勉強しようとしているか」「やるべきことがどれぐらいやれているか」ということです。これらが要領を得ないと勉強は機能しませんし、テストへの備えもできません。これまで2回行われたテスト結果と、お子さんの家庭勉強の状況を照らし合わせ、お子さんとこの1か月の学習を振り返ってみてください。勉強がテスト結果に反映されない原因は必ずあります。そこに気づき、少しずつでいいですから改善をはかっていくようお願いしたいですね。繰り返しになりますが、子どもの自立勉強は不完全なのが当たり前です。自立度を高めるべく努力しながら受験に臨み、受かったなかから進路を選び、そこからまた努力を継続していけば、将来に向けた展望は必ず開けていきます。
ある本を読んでいると、子どもの自立勉強に関する著述が目に留まりました。自学自習で東大の理Ⅲに合格されたかたの著作にあったのですが、つぎのようなことが書かれていました。“人から与えられたことをきっちりこなせるようになってはじめて、自分で計画して実行できるようになる。私のように家庭で人から勉強を強制される経験をさせてもらっている子はよいとしても、そうでない子どももいる。だから、少なくとも小学校6年間は下手に自主性を重んじたりせず、自ら学ぶ力をつけるための基盤をつくらせるべきだと思う”(引用・改編)――これを読んだとき、「なるほど」と思う反面、大人による強制をよしとしておられる点や、「自主性よりも自ら学ぶ力をつけよ」といった考えに若干違和感を思えました。しかし、先を読み進めるうちに、そのかたの親はあてがった勉強をうまくやりこなせなくても決して叱っておられなかったことがわかりました。また、よい点やがんばった点を決して見逃さず、大いにほめておられました。だから親の導きを信じてがんばり、やがて勉強を自分自身のものとして受け入れ、自分で這い上がっていく勉強法を身につけられたのでしょう。
昨年、私学の先生を何人かお招きして催しを行った際、ある先生がたまたま息子さんを弊社に通わせてくださっていることを知りました。お子さんの勉強ぶりを見て、その先生は「この年齢で受験勉強を子ども一人でするのは無理だと思った」という率直な感想をお話しくださいました。その先生は、わが子が今取り組んでいる勉強はどのようなものかということを調べ、わが子がどれぐらい自分でやれているのかを把握し、そのうえで何についてどこまで手を差し伸べるべきかを考えてサポートされているのだろうと思いました。その点で筆者は最低の親だったと反省しています。かつて愚息を弊社の某校舎に通わせたのですが、仕事柄夜中に帰宅することが多く、とうとう一度もわが子の勉強に関わることなく受験させてしまいました。当然ながら、結果も期待とは程遠いものでした。それでも本人は「受験を経験してよかった」と思っているようで、今では希望する職に就いてそれなりに生きがいのある人生を送っています。少なくとも、わが子の勉強に過剰に介入しなかったことだけは正解だったと思います。
以上から保護者にお伝えしたいのは、「自立勉強に向けて少しずつ成長していく流れを築きながら、受験で求められる学力にどう漕ぎつけるか」という視点に立ち、子どもの勉強に付かず離れずの距離を保ちながらのサポートをお願いしたいということです。適切な応援がどれぐらいのものかはなかなかわからないものです。しかし、親の愛情深い一生懸命な応援を背にした子どもは、自分でやれる範囲の努力を惜しみません。全て親頼みの勉強や、親に「自分でやりなさい」と突き放されての勉強では、子どもの自発的な取り組みは期待できませんし、成果もあげにくいものです。
今回の記事がお役にたつかどうかはわかりませんが、親としてわが子の受験勉強にどう関わったたらよいかについて思案しておられるご家庭、お悩みのご家庭にとって多少なりとも参考になれば幸いです。小学生の子どもの成長力はすばらしいものです。それを引き出すべく、親として悔いの残らぬサポートを実践してください。
※テキスト、カリキュラム、授業、家庭学習のシステムなど、弊社の学習指導に関わるものは全て子どもたちの自立学習支援を軸に据えたうえで考えられています。
カテゴリー: 子どもの自立, 子育てについて, 家庭での教育, 家庭学習研究社の特徴
2025 年 3 月 14 日
「うちの子はやる気がなくて、いつもイライラしてしまいます」「どうしてわが子はこんなに意欲がないんでしょうか」――ときどき、このような相談を受けることがあります。かつて国語の指導現場にいたとき、保護者面談の際にはこの種の話題が頻繁に出ていたのを思い出します。そこで今回は、中学受験をめざして勉強している子どもたちのやる気や意欲を高める方法についてともに考えてみようと思います。
「学習意欲が高いと、同じ勉強をしても多くの成果が得られるだろう」と、誰でも思います。だからわが子に「もっと意欲を!」と願っておられるのでしょう。では、その意欲とはどういうものかと問われると、「やる気があること」としか思い当たらず、堂々巡りになる人がおられるかもしれませんね。学習意欲とは、学ぶことへの欲求が高まり、その欲求を実現しようとする心の働きを言います。ただし、子どもが学ぼうとするのは、単純に「知りたい」という純粋な好奇心から来る欲求だけではありません。進学目標ができたから、親に認められたいから、自分の可能性を確かめたいから、新しい何かを知ったときの喜びを体験したからなど、欲求を喚起する動機づけは様々です。そこで教育心理学、学習心理学などの書物を繙き、今更ですが学習意欲とはどういうものかを整理しカテゴライズしてみました。
学習意欲とはどのようなものか
1.自分を高めるために努力しようという心の働き(自己向上心)
2.他者に認めてもらいたいという心の働き(承認欲求)
3.途中でやめずに最後までやり遂げたいという心の働き(完遂欲求)
4.ある目的のために、他のことを我慢しようという心の働き(自己制御)
5.他者に言われるのでなく、自分から進んでやろうとする心の働き(自発性)
6.他者に頼らず、自分の力で解決したいという心の働き(自立性)
上記は、専門書の著述をもとに筆者がまとめたものです。カッコ内は、保護者の記憶に残り易いよう簡潔に言い換えた言葉です。6つがどれぐらいお子さんに備わりつつあるでしょうか。こうしてみると、学習意欲は生まれつき備わっていた要素が年を経るほどに顕在化していくというよりも、子育ての過程で保護者が育んでいくべきもののような気がしますが、どうでしょうか。もしもそうなら、子どもに「もっと意欲をもちなさい!」と要求しても意味がないことがわかりますね。
1.自分を高めるために努力しようという心の働き(自己向上心)
子どもの勉強は親の接しかたで変わります。日々努力を奨励し、その日その日に日課として定めた勉強に一生懸命取り組んでいたなら、テスト結果がどうであろうとまずは努力したことを大いにほめましょう。「テストは残念な結果だったけど、あなたはとてもがんばっていたよね。おかあさんはそれがうれしいよ」と伝えてやるのです。子どもは誰でもよい点を取りたいのですから、親の声かけに反応し、「何がいけなかったのかな?」と振り返ります。このくり返しと取り組みの修正が結果に表われ、自己向上心を一層高めるという好循環が生じるのではないでしょうか。
2.他者に認めてもらいたいという心の働き(承認欲求)
最近、フィギュアスケートでメダリストをめざす少女(もはや年齢的に遅いとみなされる10歳頃からスケートを始めた)を主人公にしたアニメが人気だそうですが、その少女のコーチのほめ上手ぶりが話題になっていました(このコーチも、かつてオリンピックのメダリストをめざしたものの、挫折した経験がある)。うわべのほめかたではなく、子どもの演技技術上達の陰にある工夫や努力の積み重ねに目を向け、子どもの心に響くほめかたをしているのだそうです。大人の真意を子どもは見抜きます。単なるアニメのつくりごとの域を超え、真理をついた話だと思いました。みなさんも、お子さんの毎日の何気ない取り組みの中によい点を見出し、ほめていただきたいですね。そうすれば、親に信頼されているという実感が、子どもの意欲を大いに刺激することでしょう。
3.途中でやめずに最後までやり遂げたいという心の働き(完遂欲求)
みなさんは「一旦始めたことは最後までやり通そう」と日頃からわが子に伝え、うまくいかなくてもすぐにはあきらめず、試行錯誤を繰り返すよう促しておられるでしょうか。ちょっと躓くだけですぐに見切ってしまう癖をつけると、何をしても続かないタイプの人間になりがちです。だからこそ、親は結果ではなく、最後まで粘り強く努力したかどうかを評価の軸に置き、その様子を応援したりほめたりすることが肝要でしょう。これがやがて成功体験へとつながります。無論、親自身のものごとに対する取り組み姿勢を子どもは見ています。そのことも忘れないようお願いいたします。
4.ある目的のために、他のことを我慢しようという心の働き(自己制御)
幼児は、「しばらく我慢すれば同じお菓子を二つをあげるよ」と言われても、今貰える一つのほうに執着しがちですが、成長につれて合理的判断ができるようになります。こうした自己制御の姿勢は、子育てで強化することが可能です。たとえば、わが子が高価な遊具を欲しがったとき、すぐには買い与えず、しばらく小遣いの一部を貯金させます。そして、ある程度溜まったところで親が不足分を足して誕生日プレゼントとして買い与えるのです。このほうが子どもの喜びははるかに大きなものになります。欲しいという気持ちを長期間維持することが、より大きな充足感につながるのでしょう。今、本音は遊びたいけど、やるべき勉強をしてから遊んだほうが気持ちよい」と考える子どもに育てたいものですね。
5.他者に言われるのでなく、自分から進んでやろうとする心の働き(自発性)
誰でもそうですが、同じことでも、人に言われてやったのか、自分から率先してやったのかによって、充足感がまるで違います。勉強もそうで、親に「凄いね。自分から机に向かったんだね」と言われたほうがずっと気合が入ることでしょう。なかなか勉強を始めないわが子にしびれを切らし、「早くやりなさい!」と叱っておられませんか?これでは勉強の自発性は育ちません。勉強に限らず、わが子がやるべきことに率先して取り組んでいる瞬間をとらえてほめましょう。そして、人にコントロールされるのではなく、自分の意思でものごとをコントロールするほうが誇らしい気持ちになるし、気合も入るということを実感させましょう。
6.他者に頼らず、自分の力で解決したいという心の働き(自立性)
これがいちばん難しいかもしれません。何事も自分でやれないのが児童期の子どもだからです。自分でやろうとする姿勢の向上は、上記の1~5の要素の進展と連動しています。ですから、「これぐらい一人でやりなさい」と命じるより、子どもが勉強課題に難渋しているときは、「難しいことをやっているんだね。ちょっと見せてくれない?」と声をかけ、一緒に考えるのもよいでしょう。そして、「つぎは自分でやりたい」という子どもの気持ちを少し刺激して手を引けばいいのです。以前も書きましたが、自分でできないとき、他者の助けを仰げるかどうかも自立の重要要素です。どこがわからないのかを子どもに説明させ、子どもの気づきを引き出す親の適度なサポートは、子どもが学校や塾で臆せずに先生に質問できる力を養うことにもなります。
学習意欲は移ろいやすい面もあり、毎日の生活で生じる出来事や他者との関係性で高まったりしぼんだりしがちです。ですから、高い学習意欲をもった子どもにするための関わりは子育ての一環として常に欠かせないものだと言えるでしょう。ご承知のように、子育てには1日たりとも休みというものがなく、毎日の生活場面で継続しなければならないしんどい仕事です。しかし、その集大成として得られるのが子どもの健全な成長です。常にベストを尽くせるとは限りません。接しかたを誤ることもたびたびです。ですが、そこまで気にする必要はありません。子どもには賢い一面もあります。一生懸命な親の真意を悟らないはずがありません。「きっとわが子はわかってくれる」と信じて、日々子どもの様子を注意深く見守り、ためらうことなく子どもを導きましょう。
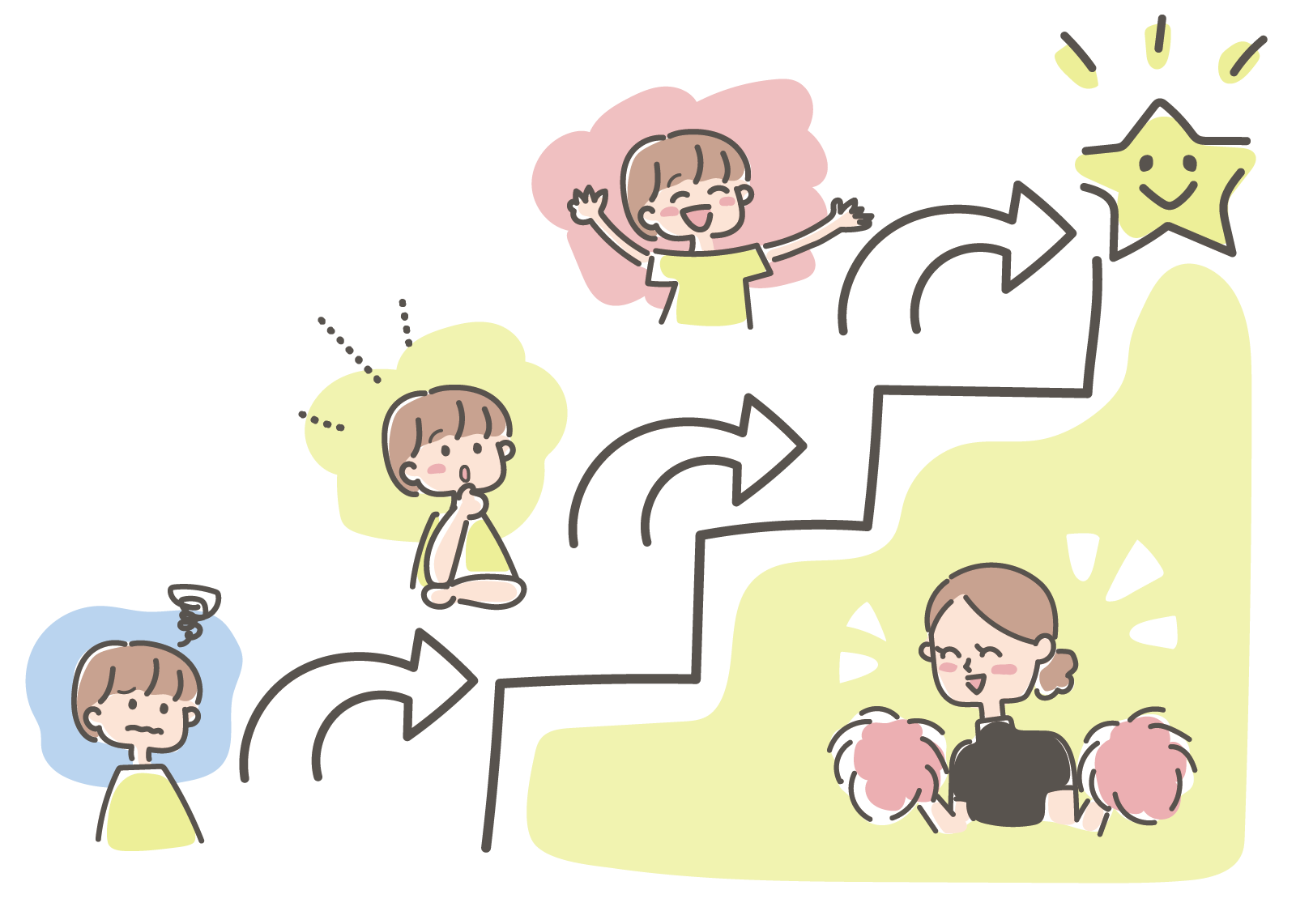
カテゴリー: お知らせ, アドバイス, ジュニアスクール, 中学受験, 子どもの発達, 子育てについて, 家庭での教育, 小学1~3年生向け
2025 年 2 月 28 日
2025年度の中学入試における弊社会員受験生の合格・進路選択状況がほぼ確認できましたので、おそまきながらご報告します。弊社は基本的にご家庭の受験校選択や進路選択に関与しませんので、以下の資料は受験生の動向調査という意味合いにおいて、これから受験されるご家庭にとっても大いに参考にしていただけるでしょう。
なお、県内の主要中学校の入試日は、基本的に重なることはありません。したがって、受験生は受けたい中学校のほぼすべてを受けることができます。弊社会員の場合、だいたい3~4校受験が主流です。ただし、なかには「〇〇中学以外は受かっても行かない」というお考えから、1校のみ受験されるケースもありますが、極めてまれです。2校・5校受験は結構あり、なかには7~8校受験の例もあります。受験校の選択は、最終的にはお子さんの学力の仕上がり状態や、通学の利便性、学校の教育環境やカラー等との兼ね合いで決めておられるのだと思います。また、お子さんの体力を踏まえ、受験日の間隔を考慮して受験校を決めることも大切でしょう。
女子の私学や共学の私学では、専願制を採用しているところが何校かあります。専願で受験した場合、入試での点数に若干上乗せがある代わりに、受かった場合はその学校に入学手続きをするのが約束となっています。実際、弊社会員家庭のほとんどは、専願で受かったら他校に合格してもこの約束を遵守しておられます。では、さっそく弊社会員の合格状況、進路選択状況をご紹介してみましょう(受験者数、合格者数の少ない中学校については、報告を割愛しています。ご了承ください)。

かねてより弊社会員の主要な受験対象校は、広島学院、修道、ノートルダム清心、広島女学院の私立4校と、国立の広島大学附属中学校でした。それは今も変わりません。資料でもおわかりのように、これらの中学校合格者の歩留まりは他の私立中学校よりも高くなっています。ただし、広島城北、安田女子、広島なぎさなどにも多数の会員が受験し、一定数が進路に選んでいます。なお、後発組の私学で近年受験者を増やしている学校があります。たとえば広島国際学院中学校には、今年弊社の会員男女合わせて40名が合格しています。この数は以前と比較にならないほど多く、しかも13名が進路に選んでいます。この私学は中学校部門を設立して歴史は浅いですが、学校の努力により年々存在の認知度が高まっています。広島市東~南部、呉市、東広島市を結んだ位置にあるとともに、周辺に競合校がないという地理的条件も同校にとって有利に働いている面もあるでしょう。AICJ中学校も、近年になって弊社からの志願者が増えています。今年は男女合わせて36名が合格し、10名が進学する予定です。英語教育に熱心なことや、インターナショナル・バカロレア(I・B)の認定資格を得られることなどが一般にも浸透し、語学に興味のある受験生(特に女子)にとってそれが魅力に映るのでしょう。
また、公立一貫校も今やすっかり人気が定着しています。右肩上がりだった志願者数がやや減少気味ですが、これは入学者選抜にあたって行われる適性検査の内容がよく知られるようになり、きちんとした基礎学力や思考力、分析力が伴っていないと受からないということが、浸透しつつあることも理由の一つかもしれません。それでも県立広島の倍率は4倍近くありますから相当な難関です。ただし、東広島市に立地するという条件ゆえ、受験生は地元の東広島市以外では、JR沿線に住まいのある受験生が大半となっています。弊社では、同校や広島中等教育学校への進学希望者の要請に対応すべく、公立一貫校の適性検査対策に力を入れています。今年は、県立広島を受検した会員受験生は53名でしたが、そのうち35名が合格しています。また、広島中等教育学校には20名が受検し、19名が合格しています。
難関校に複数合格した場合の進路選択
まずは男子受験生の動向から。今年の広島学院への合格者は64名でした。そのうち他校を進路に選んだ会員受験生は15名でした。その内訳は、広大附属4名、修道8名、県立広島2名、広島なぎさ1名(特待生)でした。広大附属に合格した男子19名のうち、他校を進路に選んだのは11名で、全員が広島学院でした。県立広島の男子合格者は17名でしたが、そのうち他校への進学を選択したのは8名で、その内訳は広大附属2名、広島学院4名、修道2名でした。
例年、女子受験生にとっての一番の憧れは広大附属です。広大附属の合格者の歩留まりは相変わらず高く、女子会員合格者12名のうち他校を進路に選んだのは2名でしたが、進学先はいずれもノートルダム清心でした。清心に合格したものの他校を進路に選んだのは19名で、その内訳は広大附属10名、広大附属東雲1名、市立中等教育1名、県立広島3名、広島叡智学園1名、広島女学院2名でした。県立広島に合格したものの、他校を進路に選択したのは5名で、その内訳は広大附属3名、ノートルダム清心1名、広島女学院1名でした。
以上、今年の弊社会員受験生の合格状況と進路選択状況をご紹介してみました。今年も例年の傾向に続いて男女ともに中学受験生の数は若干減少しています。かつて子どもの数が多く、中学受験がブームだったころと比べると随分合格を巡る競争は緩和しています。少子化と地方経済の停滞は、当然弊社のような進学塾に通う受験生の数の減少とリンクしています。実際、弊社の会員児童の数も以前と比べるとずいぶん減っています。しかしながら、その分受験生一人ひとりへの目配りやサポートは手厚くなっています。通ってくださる受験生の子どもたちが「通ってよかった」と言ってくださるよう、誠心誠意指導にあたってまいります。また前述のように、公立一貫校への進学希望者に対する進路保障はどこにも負けない水準にあると自負しています。これから塾通いを検討されるご家庭におかれては、ぜひ弊社への入会を検討していただきたく思います。
なお、志望校に進学する夢が叶えば、あとの人生が保障されるわけではありません。弊社では、ご家庭からお預かりした子どもたちがどの中学校に通うことになっても、そこでの学習環境に適応し、自分で学力を伸ばしていけるよう、自律性の高い学習姿勢の醸成に努めています。これからも、子どもたちが未来に希望をもって学び続けることを願って指導にあたってまいります。変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
今回の記事が、来年以後に受験を控えておられるご家庭にとって、多少なりとも参考になれば幸いです。
カテゴリー: お知らせ, 中学受験
2025 年 2 月 21 日
中学入試シーズンが終わり、各中学校の定数調整のための補欠繰り上がり発表なども収束しています。弊社も今年度の中学入試合格状況を公表しておりますが、本ブログで毎年公表している合格会員の進路選択状況についてはまだ確認終了に至っていません。もうすぐお知らせできると思いますのでご了承ください。
さて、今回はいつもとは少し毛色の変わったテーマに基づいて書いてみようと思います。みなさんは、性善説と性悪説という言葉をよくご存知のことと思います。性善説は孟子(もうし)、性悪説は荀(じゅんし)が唱えたものと言われています。前者は人間の本性を善人とみなし、後者は悪人とみなしていると一般に言われていますが、どちらの説も根底に教育の必要性を説いているのだという点では同じです。

この二つの説を子どもの受験指導に当てはめて考えてみたのが今回の記事です。「子どもは放っておくと怠けてしまい、ちゃんとやるべき勉強をやらないから厳しく管理し、無理やりにでもやらせないと受験での合格は覚束ない」という考えに基づく学習指導は‟性悪説”に近いものと言えるでしょう。いっぽう、「子どもは例外なく知識欲や向上心を携えている。それを上手に引き出せば、大人が無理強いしなくても自分でやるべき勉強に取り組んで、進学の希望を叶えることができる」という考えに立って学習指導を行ったとしたら、それは性善説に近いものだと言えるでしょう。
どちらの考えにも一理あり、筆者自身も若い頃には二つの考えの間を揺れていた時期があります(ただし、弊社の学習指導の理念は明らかに‟性善説”に立ったものです)。確かに、子どもは大人の環境設定や接しかた、指導の方法の如何によって、怠惰な勉強に陥ってほとんど無為な毎日を過ごすようになるおそれもありますし、逆にやるべき勉強を自ら心得て素晴らしい取り組みをしたりするようになる可能性もあります。いずれにしても人生経験に乏しい小学生であるゆえ、大人の手助けなしに受験生活を乗り切るケースは稀です。今回の記事のタイトルは、中学受験の難しさの一つはここにあると思って思いついたものです。
小学生という年齢期の子どもは何をするにも心もとないものです。その代わり、大人の保護下になければ生きていけない未熟な状態にありますから、多少の抵抗はしても結局は大人の言うことを聞きます。受験勉強においても例外ではありません。そこで保護者も学習塾の指導担当者も「やらせる」「取り組ませる」というスタイルの関わりを意識的にも無意識的にもとりがちです。ただし、どなたも「子どもが自分から勉強に取り組むよう導くのと、子どもに指示や命令を下して勉強に取り組ませるのとでは、どちらが望ましいですか?」と問われたなら、「そんなことはわかっている」とおっしゃるでしょう。自分から取り組むのがいいに決まっています。そのように導くのが難しく、多大なエネルギーを費やすことになるから、つい手っ取り早いほう、確実にテスト成果が見通せるほうを選択することになりがちなのでしょう。
つぎに別の観点から、どちらの説に基づく指導がよいのかを考えてみましょう。今や人工知能のAI時代だと言われています。AIは人手を大幅に省力化します。そんな現代社会において創造的かつ豊かな人生を送れるのは、AIのできない仕事ができる人、AIを使いこなせる人だと言われます。AIが苦手とするのはきわめて創造性の高い分野、データが活かせない、そもそもデータがない分野の仕事でしょう。このような条件下で活躍できる人間はどうやって育つのかを考えれば、性善説と性悪説のうち、どちらの考えに立った学習指導が望ましいかは明らかでしょう。勉強のよさや重要性をよく理解し、自分の取り組むべき勉強を自らの判断に基づいて取り組んだ人間のほうが創造性豊かな頭脳の持ち主になれるし、少しでも可能性を見出したなら成功するまで粘り強く物事に取り組むこともできるでしょう。
家庭学習研究社を創設した坪内茂美(故人)が、小学生の受験指導の面白さにのめり込み、現在のような指導方針、指導システムを考案した理由は、性善説に立った学習指導の優れた可能性に着目したからだと思います。子どもというものは、大人の指導の仕方ひとつで驚くほど変わり、成長していくことを実感したのです。筆者は大学で教育心理学、教育学、教育社会学を修めましたが、昭和60年に入社(広報の仕事を任されることが入社の動機でした)してから家庭学習研究社の学習指導を丹念に調べていくと、子ども自身が主体となった受験対策で合格を得るためのしくみがよく考えられていことに驚きました。あとで聞いたことですが、学習塾の立ち上げにあたって、当時教育者として高いレベルにあったかたから熱心なアドバイスをいただいて指導の方針や方法、システム等を練りあげたそうです。
このことをご説明すると長くなるので割愛しますが、ごく簡単に言うと「考えること、自分で解き明かすことの面白さを子どもたちが体感できる授業を実践すること」「家庭での一人勉強を可能にするテキスト・カリキュラムを作製すること」「小学生が無理なく取り組める学習難易度の設定(地元の最難関校に合格できるギリギリのラインを狙う)」「学習の計画性、習慣づけ、行動の自己管理面を考慮した家庭学習の応援システムの練りあげ」などです。ただし、このような要素を盛り込んだ受験対策は、家庭勉強の比重を必然的に重くします。すなわち、保護者のサポートや応援が欠かせません。当然、塾の方針や指導システムの意図をよくご理解いただく必要もあります。ただし、難しく考えるのではなく、「何事においても子どもの自立を尊重する」という考えに立って粘り強く応援すればよいのだとお考えください。はじめは苦労されるかもしれませんが、いったん勉強姿勢が浸透したなら後がずいぶん楽になります。特に、受験勉強が佳境に入る6年生の秋以降になると、保護者の負担は随分軽減されていきます。そうなると、受験の結果も、さらに先も非常に楽しみになってきます。まさに、この段階に至るプロセスはしつけ・子育ての仕上げとリンクしています。
長い間受験生と保護者を見守ってきましたが、今ものような上記のような指導方針は貫くべきだと思っています。むしろ、今日のような時代にこそ、一人でも多くの創造的頭脳の持ち主を育成すべきだと考えるからです。合格最優先なら、他によい方法があることでしょう。しかし、どのような受験結果になったとしても、そこから自分で這い上がっていけるのは、性善説に立った学習指導のもとで成長した人間だと確信しています。もしも子どもの自立という観点に立ってご家庭でお子さんの受験生活を見守り応援していただけるなら、ぜひ家庭学習研究社に入会していただきたいですね。絶対に後悔はされないでしょう。それは、立派に成長していった多数の子どもたちを見届けてきた筆者自身の経験から自信をもって言えることです。
今回の記事は、思いつきに基づいて2時間足らずで書きあげたため、文章が整っていなかったり、不適切と感じられる表現があったりするかもしれません。事情に免じてご容赦の程お願いいたします。

カテゴリー: 中学受験, 勉強について, 家庭での教育, 家庭学習研究社の特徴

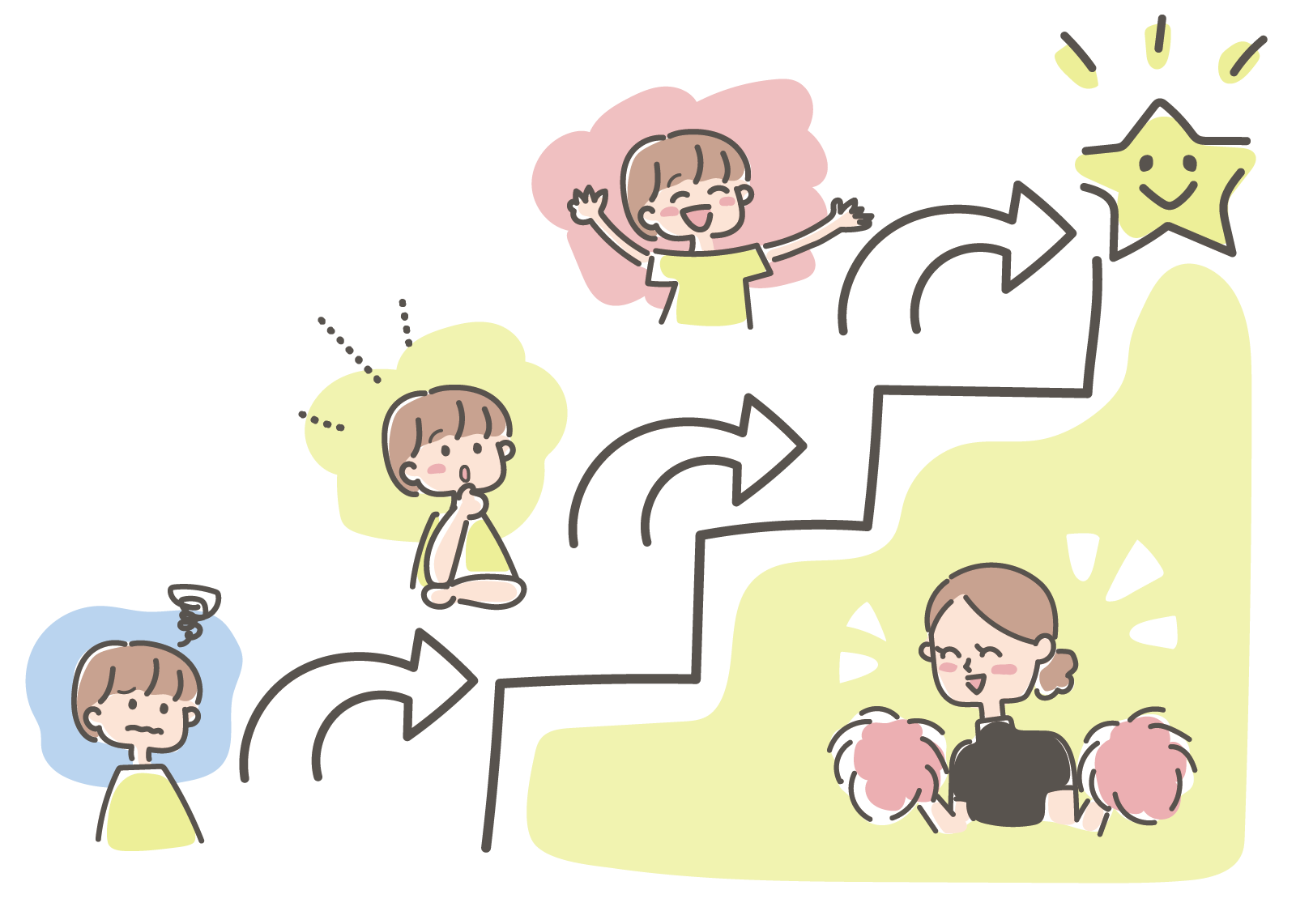



 このページは
このページは