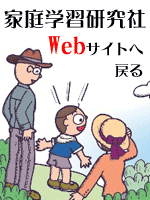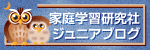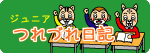子どもの「学習意欲」を高める妙案はあるの?
2009 年 6 月 15 日 月曜日
前回は、「学習意欲」と「学習習慣」とでは、どちらが先にくるべきものかということについて考察してみました。そして、「習慣づけを通して意欲が高まるのだ」という、大阪大学の志水宏吉先生の説をご紹介しました。
ただし、学習習慣は子どもだけではなかなか身につきません。ですから、親の影響力が強い小学生のうちに定着させておくのが望ましいと言えるでしょう。思春期に至ると、子どもは勉強以外の様々な楽しみを知り、友人との交流も活発化するなど、自分の世界をもつようになります。そうなると、親の話に耳を傾けてくれなくなります。
さて、今度は「学習意欲」についての話題に移ります。学習意欲と学習習慣の連動性については、すでに確認しました。学習習慣を定着させていけば、おのずとそれに伴って勉強の面白みもわかってくるという話に、納得された方も多いのではないでしょうか。
ただし、ものごとの習慣づけ自体がそう簡単ではありません(とくに、「学習の習慣づけ」はどのご家庭も苦労されていることです)。学習の習慣づけを図りながらも、学習意欲の向上につながる他の手だてについても考える必要はあるでしょう。
私たち家庭学習研究社が、「学習意欲」の向上策として大切にしていること。それは、子どもたちに「勉強の面白さ、奥深さにふれる体験を数多く提供するということです。「勉強とは面白いものだ」という実感こそが、「もっと知りたい!」「もっと学びたい!」という意欲を駆り立ててくれるからです。こういった体験は、「学習習慣」との連動性を高める相乗効果も生み出すでしょう。
学習課題について考えるとき、子どものほとんどは「これは受験のためにやるのだから、丸さえもらえればいい」とは思っていません。「何とかして課題の攻略法を見つけよう」と、必死になって考えます。そうして、課題の突破口を見つけたなら、もう有頂天になるほど喜びます。これこそが勉強の面白さではないでしょうか。
ただし、勉強の面白さを実感するには、難しすぎる課題や易しすぎる課題を与えたのではいけません。子どもが既習内容を運用し、必死になって考えれば必ず解決の突破口が見つかるような課題が適当です。
また、いちばん大切な着眼の部分を、大人に教えられたのでは子どもは喜びません。上手に、子どもたちが解決の糸口を見つけられるよう導いていく必要があります。そうすれば、どの子どもも教えられるよりも自分で解くことにこだわる積極的な学習姿勢を身につけていきます。
さて、前述の志水先生は「学習意欲」について、次のようにも述べておられます。
「『意欲』なるものは、個人のなかからわきあがってくる場合もあるだろうが、多くの場合他者との関わりのなかで育ってくるということである。食べ慣れない食べ物に手をつけるのは、親や仲間がそれをおいしそうに食べるからである。むずかしい問題にチャレンジしようとするのは、先生がほめてくれたり、競い合うライバルが存在したりするからである」
勉強は、基本としては一人ですべきものです。しかしながら、社会的動物である人間は、他者との結びつきのなかで刺激をもらい、「やってみよう!」と意欲を燃やします。とくに子どもは、手本を見てそれを真似、自分のものにしていきます(モニタリング)。その意味において、子どもの前向きな姿勢を引き出す適切な環境を与えることも有効だと言えるでしょう。
言うまでもありませんが、学習塾は子どもたちにとっての「学習環境」です。私たち自身たくさん見てきたことですが、みんなの手本になるような優れた学習姿勢を携えたお子さんがいれば、周囲が大変な刺激を受け、周囲のみんながすばらしい取り組みを発揮するようになるものです。
学習環境としての学習塾の役割を認識し、子どもの意欲溢れる取り組みを引き出す風土を醸成していきたいものだと改めて痛感する次第です。
 このページは
このページは