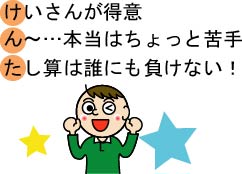台風に名前?
昨日から、いよいよ低学年部の後期講座を開講しました。あいにく開講初日は、広島にも台風が接近し、天候は大荒れでした。当日の授業は無事開講できましたが、残念ながら天候の影響により、お休みされたお子さんもいました。通学に危険を感じられた場合は、無理をせずお休みください。また、当社では、警報が発令した場合にHPやお知らせメールでご報告しています。他のメディアなどの情報と併せて参考にされながら、当日の通学をご判断ください。
台風について、気象庁のHPに台風の一生や仕組みについて紹介されていました。読むと、なるほど…と知らなかったことも多くありました。一つご紹介すると、日本では、毎年最も早く発生した台風を第1号とし、その後の台風を発生順に番号をつけていますが、実は、2000年から北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、台風委員会(日本を含め14か国が加盟)という政府組織により、各加盟国が命名した140個の名前を発生順に付けているそうです。
カンボジアが命名した「ダムレイ(=象)」を第1号につけられて以降、約5年で140個の名前を一巡し、再び「ダムレイ」の名前に戻ります。日本は、「やぎ」「てんびん」「わし」など星座の名前が採用されています。このようなアジア名をつけるようになった理由の一つに、なじみのある呼び名を付けることによって、防災意識を高める目的があるそうです。「今回の台風やぎの勢力は四国を通過し…」などいつかニュースなどで耳にする日がくるのでしょうか?
台風そのものは恐ろしいですが、調べていくと興味深い一面も。今回、思わずブログに書いてしまいました。ちなみに、広島市内には「江波山気象館」という施設があり、気象にまつわることを色々と学べます。体験コーナーでは、通常の風速から台風の風速まで体感できたり、台風の目の中を観察することもできます。一度、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
次回から、後期の授業の様子をご紹介していきます。
(makino)