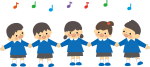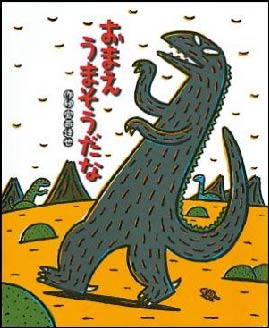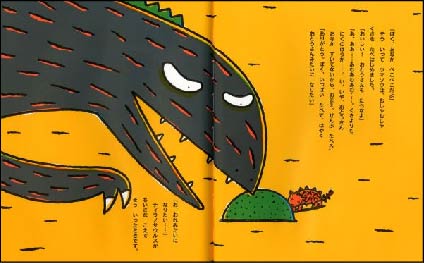空想しよう!
 『朝、学校に行ったら、学校がなくなっていて、ジャングルになっていました』
『朝、学校に行ったら、学校がなくなっていて、ジャングルになっていました』
こんなことが起こったとしたら、あなただったらどうするでしょうか?
先日のジュニア3年部の国語では、このような架空の設定から、その先の展開を自由に想像して、作文を書いていきました。
~ナビゲーターの授業アンケートから~
★「ジャングルになっていました」から、さまざまな発想がでました。「ターザンと遊ぶ」「つるでブランコを作って遊ぶ」とうれしそうに発表してくれました。
★自由にお話を作るのは楽しそうでした。「川でおぼれたねこを助けたら、ねこからの恩返しがあった…」「さるが木から落ちてしまったのは、さるすべりの木ですべってしまったから…」というものなど、キャラクターにせりふを入れてみたり、おもしろおかしい流れにしてみたりと、みな工夫していました。クラスの爆笑をかう作品もありました。
★お互いの話を発表しあい、「○○のところが面白い」「××もでてきたね。たくさん登場してきてにぎやかで楽しいね」など一人一人を評価しました。最後にナビゲーターが作った空想文を読み聞かせると、笑いながら聞き、参考になったらしく、「もっと長くなってもいいですか?」等と笑いながら再び集中して文作りをしていました。
この授業の面白いところは、「始めに起こったことが同じでも、人によってその後どうするかが違うこと」「さらにそれからどうなるかも違ってくること」です。子どもたちもお互いに発表をききながら、自分とはちがったお友達の発想や展開に、おおいに刺激を受けたのではないでしょうか(*^^*)
(S.M)